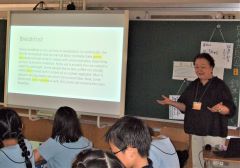![]()
世界の食と平和





二学期の終わりに、12月24日学園ミサの日の前後で、物販を行いました。心をこめて作ったレジンの小物や、文房具や小物雑貨です。ずっと販売活動をしたいという思いを持っていましたので、一つ一つ心をこめてラッピングして、看板など作って準備をしました。物販は大盛況のうちに終わりました。たくさんの人に「かわいい」「大切にするね」と購入してもらえて子どもたちは喜んでいました。年明けの1月には5年生に向けてマーケットを開催しました。ここでも沢山売ることができて、売り上げは総額30730円になりました。
それらは、当初材料費とするつもりでしたが、クラスで「募金にした方が良いのではないか」と提案があり、ほしかった粘土やカトラリーなどを購入した残りは全て募金しようということで、クラス全員の意見が一致しました。募金先はみんなで話し合って、3つの団体に決めました。アフリカなどの極貧国で食べものに困っている人たちのために日本ユニセフ協会、支援先の子どもたちの援助のためにESAアジア教育支援の会、能登など被災地支援のために日本赤十字社です。一学期からの学びで、すぐにこの支援を決める子どもたちの思いと決断力がすばらしいと思います。
年が明けて学習発表会が近づき、自分たちの思いを伝えるために調べ活動、まとめる活動、給食の食品サンプルをスキルアップさせて作る活動など、チームに分かれてそれぞれ夢中で取り組んでいきました。カレーライスや、揚げパン、フルーツポンチなどのデザートもどんどん完成していきました。発表会当日は、すてきな民族衣装でお出迎えしてくれた人もいました。みんな一人ひとり自信を持って、活動のあゆみや食品サンプル作品の説明をしっかりとすることができました。多くの人が教室を訪れてくれて、体験コーナー(紙粘土のマカロン作り)も充実していました。
「食を通じて考えてきた世界の平和について、これからも考え続けていきたい」とクラスのみんなが願っています。